

2階、壁付け終り、後ドアだけ

聚楽の壁の部屋

リビング、キッチン

建具屋が、せっせと、ドア付けています

漆喰の部屋
後、1ヶ月ありませんから


2階、壁付け終り、後ドアだけ

聚楽の壁の部屋

リビング、キッチン

建具屋が、せっせと、ドア付けています

漆喰の部屋
後、1ヶ月ありませんから
マツダキャロル

前回は2ドア、これは4ドア

デラックスの名がつく

だけあって、リアエンジングリルが、メッキ!

フロントも、少し近代的


走行4万キロ未満で、内装も綺麗

シトロエン・アミを真似たデザインのおかげで、軽にしては後席広い

前オーナー平成18年まで、大事に乗っておられた。

ずっと室内保管なので、塗装が綺麗!

スペアタイヤが、後エンジンルーム内に移されたので、フロントにトランクルームは出来た!
フロントにトランクルームを確保する為に、スペアタイヤが、リアエンジンルーム内に
普通に、乗れます



当博物館から、クルマで10分呉市中心部に、走られるとあります。
玄関入ると

昭和40年代の車が、ズラリ!
その数50台!
その内13台、ほぼオリジナルのままか? レストア終り、展示販売中
その中から、まず、マツダからご紹介させていただきます。

キャロル



この、斜めにカットされたリアのデザインは
〜

1961 シトロエン・アミのまね?
このデザイン使いましたかね?
このデザインのおかげで、後席のスペースが、確保!



内部も、オリジナルのまま!


エンジンルーム、トランク内も

平成16年1月迄、乗っておられた!
綺麗さは、トップクラスです

そうそう、この店には、当博物館の50%off券が、置いてあります。
ここに寄ってから→F Hロイス博物館、のコースが、正解かも!

前回ご紹介した、明治時代は銀行だった古民家

池のある中庭から見た所。今、月7〜8万の年金しかない方でも入れる、宅老所にしています。

日本庭園挟んで向かいは、元林酒造の牛舎の後、8人入れる宅老所。奥にもあります。
老人の皆さんは、池の鯉にエサをやったり、庭の草木の四季の眺めを楽しめます。
土地買い、建物建てて、人入れて、収益計算して、入居費用決めるのが、普通のやり方。
所謂、「ビシネスありき」
「先生!月7万円の年金で、死ぬまで、お願いします」
と、言われ、古民家を安く改装、ある時は家賃ほとんどただで、面倒見る。
所謂、「人ありき」
が、林医院のやり方。なぜかと言うと、倉橋町は広島県で1番第一次産業就業者の多い町のは一つ。国民年金受給者が、多い訳です

漆喰終わり、聚楽も

床は、長尺ビニールシート貼る準備


浄化槽も埋め、吸排水配管も着々と
左官は聚楽も終り、酒屋の大壁、1階軒下
日本語学校は?

2階第二教室、窓側が9センチ下がってるので、講師の先生がめまいするそうなので、レベル調整します。
古民家を、その良さを残したまま改装するのは、大変です。

1階教室

外観
ここは、元歯科医院兼自宅でした。
平成13年、宅老所に改装。その後学校に

因みに、これは古民家改装その2、築100年以上。銀行→駄菓子屋→しばらく放置→林医院が買取り宅老所に

その向かい、古民家改装車庫、元は、電気屋、花屋、理髪店。
祖母が筆者にくれた家、やはり築100年?
改装してシャッター付け、ロータスロイスの車庫にしていました

筆者の事務所、秘書室、定期巡回随時対応事業所サテライトがあります。
戦後すぐ建てられたスレート葺の倉庫。中は、普通の事務所。
70数年経つけど、雨漏り無し!
ものは使い様、といいますが、壊して新しいのを建てるのは、モデルチェンジして、次々と消費者に、新車を買わせる、「計画的陳腐化」の罠にはまる様なものです。
1923年、GMの創始者アルフレッド・スローンが始めた、経済手法。
これが、今人類が慌てふためいている、地球温暖化の、根本原因かとも、思われます。
また、呉市倉橋町室尾地区の、「古民家改装シリーズ」を、お伝えします
日本語学校学生寮、漆喰ほぼ終わり
酒蔵では、大きいタンクへの仕込み(添え)
甑で蒸した米を、杜氏さんが少しほぐし、12度くらいに冷やしてから、風圧で元の入っているタンクにおくります。

これは、前日の風景。右上の2つのタンクに、洗ったコメが入っています。
林酒造の本醸造は、精米率65%の八反錦という米を使っているので、このタンクの中で、2時間程水に浸します。
この「2時間」と、いうのがミソで、これか精米率70%なら4時間、35%の大吟醸なら5〜6分だそうです。
また、気温が高い時は、それより短く、低い時は長くするそうです。
また、蒸した米の手触りで、杜氏さんはこの時間を長くしたり、短くしたりするそうです。
このへんに、米の作柄や、気候が変わっても、各酒屋が毎年同じ様な味わいの酒を造れる理由があると、思われます。
日本語学校学生寮、大工仕事大体終わり

後ここに、建具屋が窓を付けます。
その建具屋は、


ドア作り。骨組みの上にシナベニア貼ります
その日本語学校

昨年4月の新入生、8人中5人が、N4の試験に合格しました!
写真の自転車は、ほとんど住民からの寄付です。
放置傾向のある、田舎の古民家を安く改装した、学校と寮。
少しでも負担を少なくする為の工夫です。
さて、酒屋では
純米大吟醸の、3段目の仕込み

純米大吟醸、仕込み終わり。
この低温醸造室は、当社GJキャメルが、施工しました。
室は4度に冷やされでいますが、この2重になっているタンクの内腔に冷水を通して冷やします。右が冷水機
日本酒は、ゆっくり発酵を進めるほど、円やかな味となります。
純米大吟醸の場合、40日ほどかけます。
冷やし過ぎると、菌が死んでしまいます。当社の杜氏は、ギリギリまで冷やすので、蔵人はヒヤヒヤするそうです。

1階では、来週からの本醸造の仕込みの準備
右の丸いのが甑。左のビニールがかかっているのが、放冷機。
蒸した米をほぐして、12度位迄冷やしてから

この、酛の入っている大きなタンク(3000リットル)に入れます。
これは、エアコンなしの酒蔵、室温で行うので、毎年一番寒いこの時期にします。
要するに、外気温か12度以上の時は、それ以上冷やせないので、仕込めないと言う事になります。

見慣れない機械があるので、杜氏さんにきいたら、スパークリングの仕込みの時、タンクの中で冷やす機械だそうです。
このパイプに冷水を流す訳です。

因みに、これは、火入れ用、右のパイプに65度位の湯を通して、麹と酵母を殺したあと、左のパイプを入れて、一気に又冷やす訳です。
仕込んで、1番いい味になったと思われた時点でアルコール添加して発酵遠止めるのが、大吟醸。
純米大吟醸は、アルコール添加なしで、最後まで麹と酵母を働かせますが、やはり火入れはします。

林酒造で、火入れしない酒は、写真の3種類だけ。
注文を受けてから、瓶詰め、冷蔵保存してもらうので、可能となる技です。
室温で長く置かれると、どう味が変わるか?わからないので、普通は余りしないそうです。
杜氏さんに聞くと、火入れすると、やや味が鋭くなる。との事です。
今日。広島は、雪で身動き取れなくなるかも?と、思い、林酒造で酒造りの勉強をしました。

大工1、2階にトイレ用の小部屋壁作る

1階、キッチン付きリビング、
キッチン側の腰壁作り。新しいサッシが入る予定。
コンパネで蓋

その壁が出来ると、筆者がネットで買った、このシステムキッチンが2組入ります。

左官の漆喰塗りも、ボチボチ進んでいます。
大工2は?

委託の仕事。「集散場」と言う、コンビニみたいに、なんでも売ってた所。土間に、床を組んでいる。
ここは、1階から見上げると、2階にもいろんな商品が並んでた。

その、外側
酒蔵では、本格的に仕込みが始まります。

袋に米を入れて水に浸け

これ、甑で蒸します。気温によって水に浸ける時間を変えます。これにより、外気温が変わっても、それぞれの酒屋が毎年同じ味わいの酒ができる訳です。
ストップウォッチなどない江戸時代は、どうやってその時間を測ったか?
その回答は、後で〜

蒸した米は、この放冷機で、十数度迄冷やしてから、ムロで増やした酛の入っているタンクに入れます。
このステンレスメッシュの速度を調整することにより、希望した蒸し米の温度となります。
4年前迄は、この3倍の幅の放冷機を使っていました-なぜこの狭いタイプに変えたのか?
その理由は:杜氏と蔵人が両側から、蒸し米を必要により、ほぐすわけですが、より丁寧に均一に出来るからです。
さて、先ほどの、時間調整の方法は?
回答:酒仕込み唄を、何節歌ったかで、調節する!
でした。

やはり、日本酒はすごい!
① 醸造酒で、世界一のアルコール濃度を達成!
② どんな米の作柄、気候の変動に、関係なく、客酒屋がそれぞれ同じ味わいの酒を造る!
ワインみたいに、「何年物がいい」なんて事はありません。
この意味で、杜氏は、科学者でもあります。



酒蔵、着物を含めて、日本文化を残すのも、筆者の使命でもあります。
だから、サクラダファミリアになっても仕方ありません。
長い間、御拝読ありがとうございました。
追伸‥
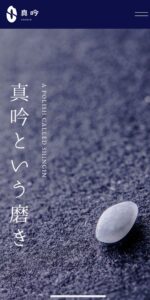
忘れていました。
今年から、精米方法をこ「真吟」に変えました。
その理由は?
今までの精米法だと、ラグビー型の米が、真円:サッカーボール型になります。しかしこれでは、尖った両側がより多く削られるので、米の外側の雑味の多い部分が、均一に削られたとは、言えません。
ラグビー型がそのままの形で削られると言う事は、雑味部分が均一に削れられたと、言う事です。
この精米機を、開発したのは、サタケ!
さすがです。
この精米法だと、65%の精米率で、50%台と同じになるそうです。
当林酒造も、サクラダファミリア。
先がまだ、見えません
御拝読、ありがとうございました。


パイレーツは、調味料を出来るだけ使わない調理法を使っています。


美酒鍋:三谷春の純米酒4合、仕込み水に、わずかなブィヨン入れて煮込みます。食材により、入れる時間を変えて、最適な煮具合にします。
客食材の持つ微妙な味で、オーケストラのハーモニーの様な、自然の塩のある美味しいスープが出来ます。

ビーフは100草食牛!さしがなく、自然な色。牛は、妊娠中、幼少期、栄養価の高い配合飼料を食べさせるのが、普通です。
先祖代々野山を走り回らせ、草だけ食べさせて、牛を育てる牧場は、オーストラリアでも3ヶ所位しかないそうです。だからA5の肉くらいの値段がします。

パスタ、蕎麦ランチの、オードブルについています。写真の左中:大根おろしと醤油で味付けしています。
「自然の味」を、お楽しみください。