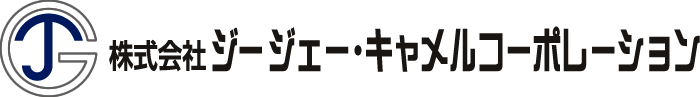直列6気筒エンジンのねじれ振動の問題を解決しようと、いろいろ骨をおり、頭を使い果たしたロイスは、2気筒を3個つなげるそれまでのやり方では解決しないという結論に達した。そこで、全く新しいエンジンの設計に取り掛かった。ロイスが最初に造ったエンジンは、2気筒10馬力、3気筒15馬力、4気筒20馬力であった。その内、2気筒とそれを2個繋げた4気筒は、振動の問題があった。また、その後生産した2気筒を3個連ねた6気筒は、クランクシャフトのねじり振動も起きていたのであった。生産効率が悪く6台で生産中止されたが、3気筒には振動の問題はなかったが、偶力(物体の異なる2点に働く力で、回転運動を生じる)を抑える必要があった。
ロイスは、3気筒を2個連ねるというやり方で、振動を抑え、偶力を相殺し、2つの問題を解決した。しかしこの形式では荷重特性が不均衡であるため、クランクシャフトを長く頑丈にし、7個のメインベアリングで支えるようにした。また、このシャフトを中空とし、圧力をかけてオイルをベアリングに送り込むシステムとしたが、これは、お蔵入りしたV8気筒エンジンに採用したものであった。
しかし、このエンジンの最大の特徴は、SV(サイドバルブ)の採用である。それまでのOHV(オーバーヘッドバルブ)から、SVにしたことによりプッシュロッドが無くなり、騒音の一つが減った。さらにタペットを調整して騒音をさらに少なくした。ロイスはチェーン駆動に反対で、クランクシャフトやデストリビューターを駆動するのはギア、冷却ファンを回すのにはベルトを使い、さらに騒音は減った。
このエンジンの開発は、1906年の夏から冬にかけて行われたが。試作車が出来上がると、ロイスはそのベアシャーシーに乗って帰宅し、週末に苛酷なテストを繰り返した。ある週末、試作車のエンジンブロックが割れた。ロイスは月曜の朝工場に行き、そこにあった13個のエンジンブロックを、14ポンドのハンマーで叩き割った。そして詳細に断面を調べ、鋳造時の中心の位置がずれているのを突き止め、直ちに解決策を指示したという。
こうして、ロイスのどんな細かな問題でも発見、そして分析、的確に解決の答えを出すという、素晴らしい能力:①で述べた「天才」としての能力、が発揮され、当時類を見ない静かなエンジンが出来上がった。
また、このエンジンの補機類がまた、素晴らしかった。
電気系統の品質は、世界で初めて火花の飛ばないモーターと発電機を作り上げ、電機メーカーとして成功したロイスの得意分野だけあって、他のメーカーに比べ、飛びぬけて優れていた。
デストリビューター、振動式点火コイル、高圧発電機はロイス自身が造ったものであった。当時はコイルを使ってエンジンを始動、それから発電機の電気でプラグに火を飛ばして走り続けるという方法で、蓄電池の放電を少なくした。しかし発電機の性能が悪かったので、トップギアでゆっくり走る時は両方の点火装置のスイッチを入れておくことが必要であった。後の話となるが、1919年になると発電機の性能が向上し、前照灯と始動モーターに十分な電気が供給できるようになる。
この新エンジンの振動式点火コイルは、強い火花を飛ばすことが出来たので、点火時期調節レバーを動かして、デストリビューターの接点をぱちぱちと断続してやれば、6気筒のどれかのシリンダーの中に残っているガソリンに点火し、エンジンが始動した。こうすると、重いクランクを人力で回したり、蓄電量の少ないバッテリ-の電気を消費して始動モーターを使うことなく、エンジンを始動させることが出来た。
筆者も、あるクラシックカーの集まりに1935年製25/30に乗って行った時、このことを車に詳しい人から質問されたが、実演はしていない。
制動装置(ブレーキ関係)の機構も、他のどの自動車より洗練され、的確に作動した。当時ロールスロイスに乗る人たちは、ステアリング、シフトレバーなど主な操作機器から、ごく小さなレバーやスイッチ類まで、優れた工作機械のように正確に加工され、取り付けられていることに感動した。
この車が最初に紹介されたのは、1906年11月15日、ロンドン・オリンピア・ショーで、そこで人々は美しく輝くパルテノングリルに感動し、大好評を得た。しかし、それにも増して、ロールスロイスが一般大衆の注目と称賛を浴び、世界一の称号を得ることとなったのは、1907年7月にクロード・ジョンソン自らが行った苛酷なテスト走行の結果である。
このテストは、クロード・ジョンソンも所属するRAC(王立自動車協会)の監督のもとに行われた。この時に使用した40/50型は、新設計により製造されたシャーシーの内、13台目のものに銀色に塗装されたツーリングボディを乗せ、金属類は全て銀メッキがなされていた。そしてこの車のフロントグラス下には、「シルバーゴースト」と記した鋳物のプレートが燦然と輝いていた。
他の自動車が、けたたましいエンジン音などを発しながら走ったこの時代、音もなく静かに現れるこの車に「シルバーゴースト」の車名はピッタリであった。また、マネージャーとしての才能に長けていたクロード・ジョンソンは、このテストの期間中、大衆の注目を集めるように様々な努力をした。
テスト走行の初めはベクスヒルからグラスゴー間往復、計3200キロで行われ、直結の3速と、オーバードライブの4速だけを使って、RACが開催予定としていた:スコットランド・トライアルの様式で走った。この後、シルバーゴーストは分解され、RACの技術者によって細かく検査された。技術者たちはわずかな欠陥も見逃すまいと、文字通り微に入り細を穿って検査を施行したが、1つのピストンリングにいくらかのガタがあった他は、すべて完全であると報告した。
このシルバーゴーストは再び組み立てられ、スコットランド・トライアルに出場、速度、信頼性、燃費の総合評価で金賞を獲得した。その後ロンドンーグラスゴー間を何度も往復し、24,000キロ走るまで、休みなくテストが続けられた。この間のトラブルは、スコットランド・トライアル中に、燃料コックが緩んで「止」の位置になった時だけであった。シルバーゴーストは再び分解され、同じ検査を受けた。RACの技術者は、操向機構の一部にわずかな摩耗がみられ、冷却水のポンプのパッキンを交換する必要があることを指摘した。これは、すぐ修理するほどのものではなかったが、ジョンソンは交換を命じ、部品代は2ポンド2ペンス7シリング(現在の\2,288)であった。
また、その時の燃費は1Lあたり6.3キロであった。当時のガソリンはオクタン価60~70であったと考えられ、7,036cc直6エンジンでのこの数字には驚かされる。
この、数々の栄光に飾られた40/50シルバーゴーストは、その後何人かのオーナーの手を経て、80万キロ走破、1948年にロールスロイス社に買い戻され、現在でも走行可能である。何らかのクラシックカーのイベントで先頭を走ったという話も聞いたことがある。
⑩でも述べさせていただいた通り、「究極の経済車」であることは間違いない。
時は、新型コロナウイルスが地球上に蔓延し、街から車が消え、工場の生産も止まり、CO2の排出も自然に削減されている。ひょっとしたら、地球が自分の身を守るためにこのウィルスを創造したのかもしれない。GMの創始者:アルフレッド・スローンが始めた「計画的陳腐化」の企業戦略にのせられて、次々と新車に乗り換える現代人に警鐘を鳴らしているのかもしれない。
少なくとも20世紀初頭の、FHロイス氏や、クロード・ジョンソンをはじめとするRACのメンバー達、また、車を発明したカール・ベンツ、車を庶民のものにするために努力したヘンリー・フォードらは、人々の役に立ち、社会貢献するのが目的で、車造りに専念していたことは確かである。
令和2年4月3日
林英紀